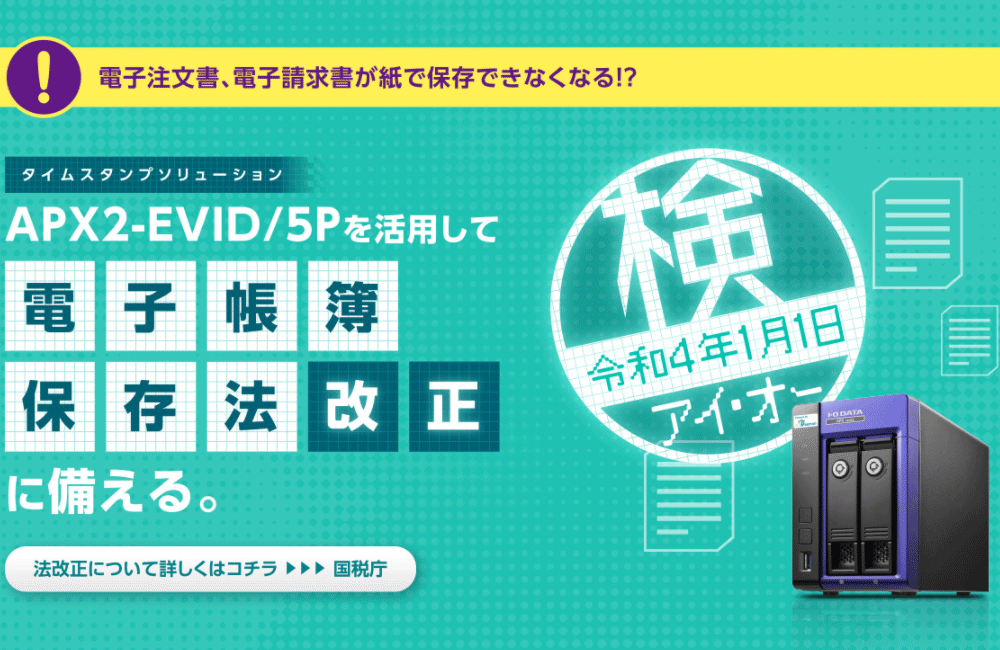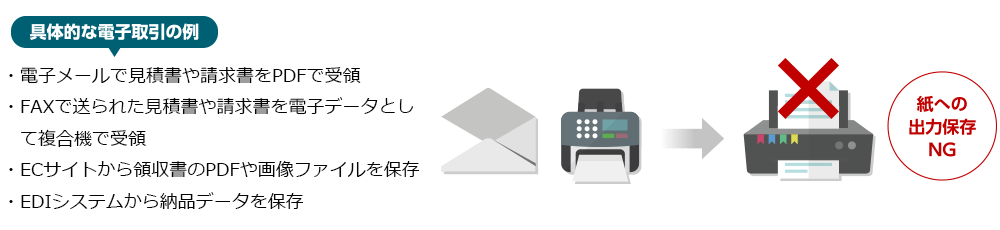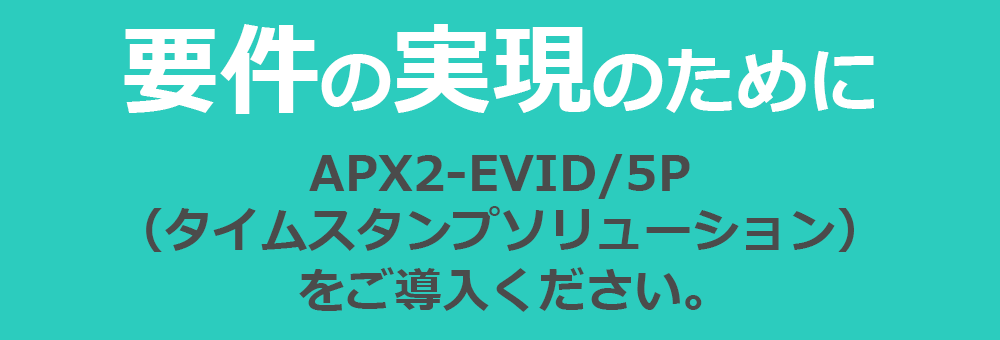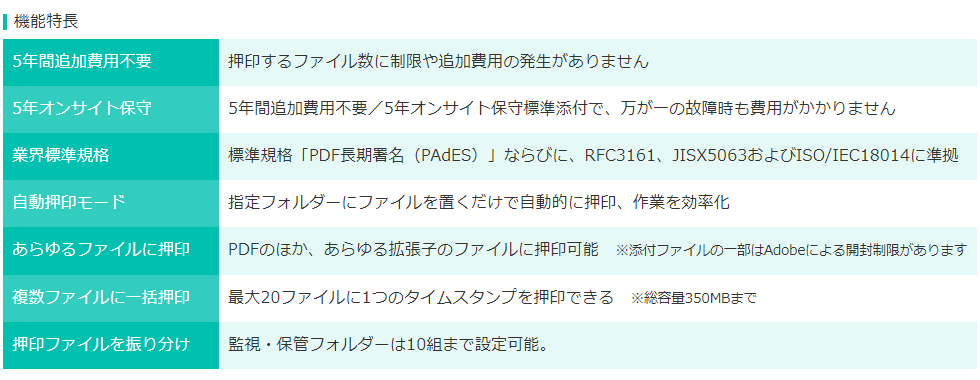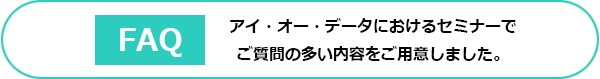電子帳簿保存法改正特集ページ(電子取引・電磁的記録)
-
テレワークの拡大で、企業ではメールで見積書や注文書を送ることが当たり前になっています。しかし電子帳簿保存法(電帳法)の改正に伴い、令和4年(2022年)1月1日以降は、これら電子取引での取引情報を紙に印刷をして保存書類とすることは認められず、電磁的記録の保存が義務付けられます。
-
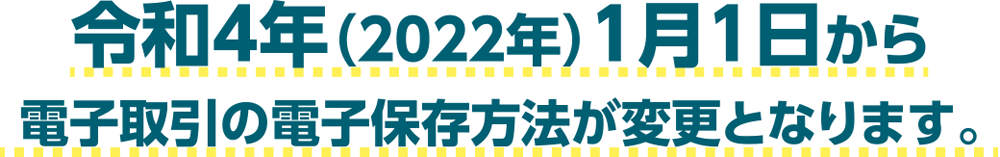
-
電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)の改正のポイントは次のとおりです。
-
【1】事前承認制度の廃止(緩和)
-
国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存を行う際に必要な所轄税務署長の承認が不要になります。
-
【2】スキャナ保存の要件緩和
-
国税関係書類をスキャナ保存する際の適正事務処理(相互けんせい、定期的な検査、再発防止策の社内規定整備)等が不要となります。
-
【3】電子取引の電磁的記録の義務化
-
これまで認められてきた、電子取引(※1)での取引情報(※2)を出力した書面は保存書類として取り扱わないとされ、電磁的記録として定められた要件に従って保存することが義務付けられます。
-
※1 電子取引とは
以下いずれも「電子取引」です。特にコロナ禍において(1)(6)のような運用を導入されている企業も多いのではないでしょうか。
(1)電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領。
(2)インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)、またはホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用。
(3)電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用。
(4)クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用。
(5)特定の取引に係るEDIシステムを利用。
(6)ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用。
(7)請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領。
※2 取引情報とは
注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、その他これらに準ずる書類。
この中で注目すべきポイントは「【3】電子取引の電磁的記録の義務化」です。これまでの電帳法で認められてきた、電子取引における取引情報の紙に印刷して保管する方法が、令和4年1月1日以降認められなくなり、電磁的記録の保存が義務付けられました。例えば、現在複合機のFAXやメールで授受しているPDFファイルの見積書や注文書、請求書などがある場合、電子取引の取引情報は紙での原本保管は認められず、全て電磁的記録を行う必要になります。
-
電磁的記録には タイムスタンプ利用がおすすめ
-
電磁的記録をする場合には、「真実性」「可視性」が求められています。
専用のシステムを導入するハードルの高さや、管理規程を運用する煩雑さを考えると、真実性を確実に証明可能なタイムスタンプの付与ができる本商品(APX2-EVID/5P)の導入がおすすめです。
本商品には、ファイルに付与されているタイムスタンプが有効かどうかをまとめて確認し、一覧表示できる「一括検証機能」も搭載しているため、ファイルが多くなっても容易に管理することができます。
※指定したフォルダーに保存されているファイルが対象です。
-
▼ 真実性について
-
以下のいずれかの方法で、真実性を担保する必要があります。
(1)タイムスタンプを付与する。
(2)データの訂正削除を行った場合に、その記録が残るか、訂正削除ができないシステムを利用する。
(3)訂正削除の防止に関する事務処理規程で運用する。
-
▼ 可視性について
-
記録を可視できる状態として「一課税期間」を通じて検索(※)でき、ディスプレイ等に整然とした形式で出力することが求められます。
※検索機能は
・「取引年月日」「取引金額」「取引先名」を検索項目として設定できること。
・「取引年月日」「取引金額」はその範囲を指定して条件設定ができること。
・2つ以上の記録項目を組み合わせて条件設定できること。
が求められます。
具体例として
(1)検索項目をファイル名に設定し、「取引先」や「年月日」のフォルダーを作成して管理する。
(2)ファイル名と検索項目の索引簿を作成し、ファイルと共に管理する。
のいずれかの方法で検索を可能とし、パソコンへ液晶ディスプレイを接続して表示可能とすることをおすすめします。